先日、Twitter経由で「いま使っているオーディオインターフェイスの入力音が痩(や)せていて、使いものになりません。USB 1.1対応のオーディオインターフェイスであることが原因だと思いますが、2.0対応にすると入力にどの程度の差が出るでしょうか?」という質問をいただきました。さらに「それ以前に使っていた機材でも、音痩せを感じていました。やはりUSB 2.0のなるべく高価な機種のほうが良いのでしょうか?」というメッセージが来ていたのです。
個別の質問にはお答えできないケースも多いのですが、今回の話はちょっと気になったのと、ありがちなミス、勘違いが原因なのでは……と思い、やり取りした結果、うまく解決することができました。同じような間違いで、オーディオインターフェイスを正しく使えていない人も多いように思ったので、改めてオーディオインターフェイスの正しい使い方について考えてみたいと思います。
 あなたのオーディオインターフェイス、正しく使えていますか?写真はRoland DUO-CAPTURE EX
あなたのオーディオインターフェイス、正しく使えていますか?写真はRoland DUO-CAPTURE EX
予め断っておくと、音質の評価というのは非常に難しく、私自身も苦手なほうです。オーディオ評論家の先生方は、ほとんど差のないような音の違いを文章にして評価されているので、スゴイなと思っているのですが、すごく耳のいい人、毎日音を作りこんでいるプロの方だと、微妙な差が致命的に思えるほどに感じるのだと思います。そうした場合、ある意味、音の好き・嫌いというところになるため、アドバイスも難しくなりますが、今回のケースはちょっとそうではないように感じます。
まず最初にお答えしたのは、「USB 1.1とUSB 2.0の違いで音質に大きな差が出るわけではない」ということです。確かに規格上USB 1.1だと最高で24bit/96kHzまでしか扱えず、しかも録音・再生を同時に行うDTMの使い方においては24bit/48kHzが限界。24bit/96kHzや24bit/192kHzが扱えるUSB 2.0と比較するとフォーマット上の音質が劣るのは事実ではあります。でも、これは微妙な音の違いであり、ちょっと聴いてすぐ判別できるようなものではないし、明らかに音が変質する「音痩せ」の原因にはなりえません。
 Mackieのアナログミキサー、写真は802-VLZ3
Mackieのアナログミキサー、写真は802-VLZ3
だから、「今回のケースはアナログ側に原因があるのではないでしょうか?」とお返事したのです。すると「“アナログ側に原因”とはどのような意味でしょうか? ちなみにMackieのミキサーのメインアウトからオーディオインターフェイスに接続しています。レベルオーバーは起こしていません。DAWはAbleton Liveです」、「Mackieのヘッドホンアウトから直接聴く音と比べると、極端にコンプレッションがかかったような音になるのですが、何に原因が有るのでしょうか? お知恵を拝借出来れば幸いです」という連絡がありました。
みなさんは、なぜこうした現象が起こったのか原因が分かりますか?これだけの限られた情報で原因究明するのは難しいところではありますが、「もしかして?」と思い、次のような返事をしました。
 オーディオインターフェイスのインプット端子に入力し、入力レベルは最小に設定する。写真はQUAD-CAPTURE
オーディオインターフェイスのインプット端子に入力し、入力レベルは最小に設定する。写真はQUAD-CAPTURE
「Mackieの出力を割れない範囲で大きくして(0dB設定できるなら、そのように)、オーディオインターフェイスの入力ゲインを最小にして試してみてください」と。結果はビンゴだったようです。
知っている人なら当たり前、知らない人にはとっても不思議な話ですが、これ、最近の多くのオーディオインターフェイスで、非常にありがちな使い方のミスですね。先日の「DTM初心者のためのオーディオインターフェイス選び 」という記事でも紹介したとおり、オーディオインターフェイスの多くは、1つの入力でライン入力、マイク入力、ギター入力などを兼ねており、それに適した入力をしないと、音が変質してしまいます。
 入力レベルの調整はオーディオインターフェイスによって表記に違いがあるケースもあるが基本はどれも同じ
入力レベルの調整はオーディオインターフェイスによって表記に違いがあるケースもあるが基本はどれも同じ
今回の例だとミキサーのメイン出力を突っ込んでいるということですから、ラインレベルでの信号、つまり非常に大きいレベルの信号が入ってきています。その場合、オーディオインターフェイスはラインレベルに合わせて最小に絞る必要があるのです。オーディオインターフェイスによっては、左に回すと「LINE」、右に回すと「MIC」といった記載がされていますが、そうでない機器も同様です。
先ほどの方からは「指示通りの操作で問題が解決しました!オーディオインターフェイスのSENSって最小でも音が入るんですね……。あと、レベルオーバーしても音割れせずに自動でコンプレッションがかかるとは知りませんでした。そもそもマイクもラインも同じ端子から入力するんですね、今更ですが……」との連絡があって、無事解決しました。
レベルオーバーした際、自動でコンプレッサがかかるかどうかは、製品によっても違います。基本はレベルオーバーしないようにすることが大原則です。でも、この「入力レベルを最小にすると、音が入らないのでは…」という勘違いは非常にありそうですよね。
多くのオーディオインターフェイスには、マイク用のプリアンプが内蔵されており、この入力レベルを上げることで、マイクプリが動作しだします。そう、ラインレベルと比較してマイクの入力は非常に微小だから、アンプが必要なのです。しかし、マイクプリ単独の製品も数多くあり、価格も高いものだと数十万円もすることからも分かるとおり、これを通すことで音量が上がると同時に音も変化するのです。
 1つの端子がマイク入力、ライン入力、ギター入力を兼ねているオーディオインターフェイスが大半。写真はUS-366
1つの端子がマイク入力、ライン入力、ギター入力を兼ねているオーディオインターフェイスが大半。写真はUS-366
しかし、今回の例ではミキサーで作った音をレコーディングするのですから、マイクプリは不要。そのため、最小に絞っておく必要があるわけですね。ちなみに、この方の場合、マイク、楽器、オーディオ機器の音をミキサーでまとめた後に、オーディオインターフェイスへと接続していたわけですが、できるだけいい音で録るのであれば、できれば直接オーディオインターフェイスに接続することをお勧めします。
レコーディングの基本は、なるべく音源に近くして録ること。つまり、間にミキサーやパッチなどを入れず、できるならエフェクトも通さず、ケーブルも短くして録音したほうが、いい音で録ることができます。ミックスが必要なら、DAWでミックスするほうが、音質的には有利ですからね。
 24in/24outの入出力を装備するUSB 2.0対応オーディオインターフェイス、Steinberg UR824
24in/24outの入出力を装備するUSB 2.0対応オーディオインターフェイス、Steinberg UR824
もし、どうしても複数楽器の音を同時に録りたいのであれば、それこそUSB 2.0対応でマルチポート入力を持ったオーディオインターフェイスを入手して行うのがいいですね。
いまのオーディオインターフェイス、どれも非常に高性能ですから、製品による音質の違いはそれほど極端なものではありません。機器ごとによる音質の違いよりも、間にミキサーを通すかどうかのほうが、遥かに音質を劣化させますから、その点もよく考えたほうがよさそうですね。
今回は、ラインレベルとマイクレベルの使い分けについて紹介しましたが、それと同時に、ギターを入力する際に、ハイインピーダンス(Hi-Z)入力の設定にしておくことも重要ですね。これをしないと、ギター音色の音痩せの大きな原因となります。ただし、これもギターやベースをオーディオインターフェイスに直結する場合の話であり、間にエフェクトやDIを挟む場合は、ラインレベルになるので、Hi-Zはオフにしておく必要があります。もっとも「ロー出し、ハイ受けの原則」というのがあるので、Hi-Zのままでも、大きな問題はないはずですが……。
新しい、高性能な機器を入手するというのは、楽しいし、それでグッと良くなる可能性もありますが、まずは手持ちの機材の使い方を見直すことで、音質を大幅に改善できる可能性もあるので、気になる方はぜひ試してみてください。
【関連記事】
DTM初心者のためのオーディオインターフェイス選び




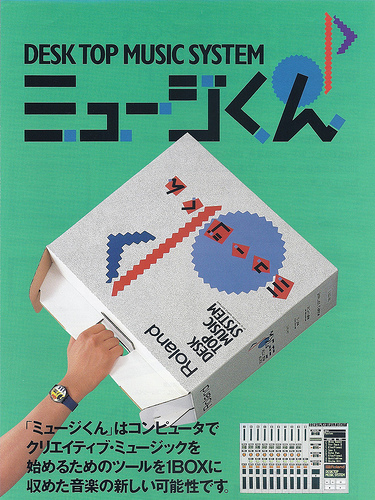
コメント
sasakure.UKファンの六花 iPadさん
US-100、いいんじゃないでしょうか…。入門機種としては悪くないとは思います。
ただし、これ16bitであり、ASIOにも非対応なので、その点は注意が必要ですね。
あくまでも入門機であるという割り切りは必要だと思います。
お返事です。突然なんですが、US-366というものを発見しましたが、
ASIOには対応していますか?もし目的が高音質化で、
録音などではなかったら、オーディオインターフェース選びは、
どうすればいいでしょうか?質問ばかりですみません。
それでは、さようなら。
sasakure.UKファンの六花 iPadさん
US-366はもちろんASIOに対応しています。
音のよしあしは、やはり自分で実物を聞き比べてみるのがベストですが、
近所にお店がないとなかなか難しいのは確かです。
スペックだけではなかなか分からないのですが、
ASIO対応、24bit/96kHz以上対応のものを選ぶといいと思いますよ。
何と比較するかですが、もしPCの標準のサウンド出力と比べるのなら、
どれを選んでも格段に音質は向上すると思います。
藤本様、こんにちは。
Native Instruments社のKontaktと、オーディオインターフェイスとの相性について質問させていただいてよろしいでしょうか?
私の製作環境を述べると、OS:Win7, DAW:Cubase7, オーディオインターフェイス:MR816csxなのですが、最近導入したKontaktの安定性がいまいちです。特にStudio Drammerを使用すると、直ぐにVSTパフォーマンスのreal-time peakが振り切れてしまいます。ちなみに、そのときのaverage loadは50%くらい、diskパフォーマンスメーターはほぼ0です。
色々いじってみたのですが、効果的だったのはMR816csxのバッファサイズを大きくすることくらいでした。ようやく安定するサンプル数が256くらいからで、このときのトータルレイテンシーは10msecくらいでした。ですが、他のソフトウェアプラグインの併用を考慮すると、もっと大きなサンプル数が必要であるように感じます。
もっとレイテンシーを小さくしつつ、安定性も向上させるためのヒントをご教示いただけないでしょうか?もし、オーディオインターフェイスの相性問題があるのなら、Kontaktと相性のよいオーディオインターフェイスの購入も考慮しています。
よろしくお願い申し上げます。
A Studentさん
こんにちは。状況からすると、とくにシステムに不具合があるわけではないみたいですね。
バッファサイズを大きくしたら、改善したということが、すべての答えにつながっていると思います。
つまり、いま使っているマシンのパワーから見て、Kontaktが重いということですね。
これは相性の問題ではなくて、PCの処理能力不足ということだと思います。
つまり、オーディオインターフェイスを替えれば、安定性が向上するとういわけではない
(若干よくなるものはあるかもしれませんが)、ということです。
これを安定的に動かすには、やはりCPUパワーを向上させるとともに、
メモリーを大きくする必要がありそうです。また、もしもOSが32bitだとしたら
これを64bitに変更するというのも大きな手ですね。
藤本様
早速のお返事ありがとうございます。
なるほど、PCの処理能力不足ですか…
重ねての質問でまことに失礼ですが、以下に私が制作しているPCのスペックを示しますので、改善できる点を示していただけないでしょうか?
OS:Windows7 Pro 64bit
CPU: Intel Core i7-2600K at 3.4GHz
RAM:16GB(DDR3-1333, 4GB*4)
SSD:Intel SSD 240GB*2
IEEE1394ボード:玄人志向 IEEE1394-PCIE
以上を、Shuttle社のSH67H3に組み込み。
バッファサイズ以外の設定変更では良い結果を得られませんでしたが、現在の設定を申し上げると
CPUのハイパースレッティングはON、DAW側のASIO GuardもON(一応Steinbergの推奨設定です)。
録音形式は96kHz-24Bit。バッファサイズは256samples。この設定だとHALion SonicやReal Guitar、Trilianといった他のソフトウェアは問題なく動きます。ですが、KONTAKTの、特にStudio Drummerは余裕がありません。
SSDを2つ組み込んでありますが、そのうちの一つにKOMPLETEのライブラリを入れており、もう一方のSSDにはOSやDAWを含めて諸々のファイルを入れています。
以上、思いつくままの説明となりましたが、改善点を示していただければありがたいです。
よろしくお願い申し上げます。
藤本様
前回の投稿から3点の変更を加えたところ、以前よりも安定性が向上しました。
Studio Drummerの音を鳴らしているときも、real time peak が振り切れる頻度がかなり低くなりました。
以下に変更点を述べさせていただきます。
1. BIOSを最新にアップデート。
2. ハイパースレッティングをoff
3. ASIO guardをoff
どれがクリティカルだったのかイマイチわかりませんが、これで全体的に安定性が向上した感触を受けています。
しばらくは様子を見ていきたいと思います。
お忙しいところ、お騒がせして大変申し訳ありませんでした。
これからも藤本様の記事を楽しんで拝見させていただきます。
A studentさん
こんにちは。お返事が遅くなってすみません。が、とりあえず解決したようでよかったです。
それにしても、PCのスペックを見る限り、十分すぎるものですね。
というか、限りなく私の使っているシステムと同じですね!
これで問題があるとしたら、
やはりKONTAKTがあまりにも重いということなんでしょうか……。
BIOSのアップデートなどで、なんとか使えるようになったとのことですが、
ほかに考えられることとしては、一緒に動かしているほかのプラグインなどの負荷が大きい
ということでしょうか…。もし、KONTAKTだけが動くようにし、ほかのプラグインをすべてオフに
した場合はどうですかね…。
私が、KONTAKTを使っていないので、あまりいいアドバイスをできないのですが、
一度NIに連絡をしてみてもいいかもしれません。
藤本様
お返事ありがとうございます。
試しにHALion Sonicのドラムセットを鳴らしながら、KONTAKTに入っているピアノ音源を使ってみたのですが、鍵盤を激しく打鍵してもreal time peakが振り切れることはあまりありませんでした。
今のところは安定していますが、再び不安定化したら思い切ってNIに連絡してみます。
私のマシンのスペックが藤本様のとよく似ているということですが、それもそのはず、藤本様が本サイトで以前公開された記事を参考に私のマシンを組み立てさせていただきました。
最新記事のUAD-2もまことに興味深いです。今後とも興味深い記事を楽しみにしております。
最後になりましたが、藤本様の一層のご活躍をお祈りしております。
A Studentさん
なるほど、そういうことだったんですね。とっても光栄です!
ぜひ、これからもご愛読のほど、よろしくお願いいたしますm(__)m
という事は、pod hd500からインターフェイスならばHi-zはきる方が良いと
言うことですよね?
sさん
はい、その通りですよ!
はじめまして
DTMを昨年11月から初めまた初心者です。
先日オーディオインターフェイスを購入しました
rolandのFA-66です。
cubaseとの相性が悪いのか、パソコンのスペック不足なのか
cubaseで作業する際だけバリバリノイズが出て作業不可です。
パソコンはmac pro(初代、2GHzのXeon×2で4コア、メモリ10GB、OSは10.7)
DAWはcubaseartist7.5です。
garagebandやitunes、WEB閲覧などではノイズが乗りません。
並行して使っているmacbookpro(core i5、メモリ8GB、OSは10.9)
ではノイズはおこらないので、初代mac proのスペック不足かなと思いますが、
お考えはいかがでしょうか。
やはり初代macproではDAW役不足でしょうか。。
動画の編集などではまだまだ現役なのですが、DAWソフトの作業というのは
どのくらいの負荷をパソコンにかけるものなのでしょうか。
DTMを始めてみて、作曲の楽しさだけでなく
ハードウェアを更新する楽しみもあり、どんどんハマっていますが、
このようにつまづいたとき相談できる場所がないのは厳しいですね。。
お忙しいところ恐縮ですが、何かお気づきの点があれば
アドバイスいただけるとうれしいです。
JCさん
こんにちは。なんででしょうね…。FA-66は基本的にAppleがサポートしてるオーディオインターフェイスなので、ドライバも不要ですぐ使えるし、Xeon×2であれば、おそらく問題ないはずなんですが…。
とりあえずバッファサイズを大きくしてみたらどうでしょうか?
藤本様
お忙しいところ早速のアドバイスありがとうございました。
アドバイス通りバッファサイズを大きくしてみたところ、症状が改善されました!
ちなみに初期設定32で、64にしたところほとんどノイズはなくなりましたが、
所々でプチプチとノイズが残ったため128に。
これでほとんど気になることはなくなりました。
適切なアドバイス頂戴し感謝いたします!
また一つ賢くなった気がします!
いつも興味深い記事、盛りだくさんで楽しく拝読しています。
こうしてアドバイスいただけて、ますます親しみやすいサイトとなりました!
陰ながら応援させていただきます!
JCさん
無事解決してよかったです!
ぜひ、ぞんぶんに楽しんでください。
こちらの記事、大変参考になりました。
私もアナログミキサー(ベリンガー1002FX)とUA-55を接続して使おうとして、
設定に悩んでおりました。
ですがこの記事を拝見し、ミキサーの出力(デュアルケーブル)をUA-55のような別途ライン入力がないものにはSENS1L,2R両方を最小(「-」になっているほう)に設定し、接続するものなんだということがよくわかりました!
本当にありがとうございます。
また、ついでに何点か質問なのですが、
UA-55にはAUTO-SENSボタンや専用のコントロールパネルにて
SENSを変更したりできますが、こちらは原則的にはいじらない、AUTOにしない、
という認識でよろしいでしょうか。
また、アナログミキサー1002FXは随分前のものとなり、大分ガタがきておりますので、
買い換えを考えておりますが、おススメのアナログミキサー等ございますでしょうか。
接続するものは、シンセサイザー数台、マイク等で配信予定中となります。
ギターやベースは接続しません。
随分前の記事への書き込みとなり、恐れ入りますが、
何かアドバイス等ありましたら幸いです。
質問事項の追記です。
こちらは現在1002FXがアンバランス出力となっており、
UA-55側はバランス入力に対応しており、アンバランス、バランスどちらでも
接続は可能かと思いますが、強いて言うならば、どちらが良い、等ありますでしょうか。
また、それに伴い、上記にておススメを既にお聞きさせていただいておりますが、
TRS出力に対応したおすすめアナログミキサーをご教示いただけましたら幸いです。
最後に、UA-55のリアのOUTはTRSバランス接続タイプのようですが、
こちらにアンバランスTSタイプのケーブルを接続し、アンプ等に出力するのは、
インターフェースに負担がかかり、あまりよくないでしょうか。
特にどちらのケーブルを使うにしろ問題がないのかもしれませんが、
ふと気になっておりましたので、お答えいただけますと幸いです。
お手数をお掛けいたしますが、よろしくお願いいたします。
Motifさん
お役に立ったようでよかったです。
QUAD-CAPTUREにあるAUTO-SENSですが、これはよくあるレコーダーのオートレベル調整とはまったく異なるものです。最適なSENSの最大値がどこにあるかを探すためのものなので、自分でSENS設定ができるのであれば、不要です。ただ、これを利用することで簡単に最適なSENS値にすることができるのでとても便利ですね。ICレコーダーなどにあるオートレベル調整は、入力レベルに合わせて刻々とSENSを調整するものなので、音楽には向きませんが、QUADのものは最大入力音量を見つけ出して、ピークを超えないようにSENS値を決めてくれるというものなわけです。
Motifさん
アンバランス対応の機材にバランスケーブルを接続した場合、何のメリットもないし、何のデメリットもありません。有効なのはバランス対応機材同士をバランスケーブルで接続した場合のみです。
藤本様
迅速なご回答、誠にありがとうございます。
最適なSENSの最大値がどこにあるかを探すためのものであるとのこと、参考になりました。
アンバランス、バランス接続についても何のメリットもなくデメリットもないとのこと、ありがとうございます。
やはりTRS出力対応のミキサーを購入検討してみます!
また、試しに、シンセ(出力80%)から直接IFへ、シンセ-ミキサー(0dB)-IF、と、
両方の設定で強めに弾き、AUTO-SENSを試してみましたが、音色にもよりますが、
つまみで言うと9時頃まで回した状態に設定されますが、
これはライン出力でも、ゲインは最小じゃなくても
このぐらいまでなら大丈夫であり、出力すべき、ということなのでしょうか。
先日ご質問させていただき、その後も調べていると、
やはりシンセサイザーやミキサーからのライン出力はマイクプリと兼用の入力に
接続する場合は、ゲインは最小に絞る、
というのが一般的なんだなぁと再認識していたので、今回AUTOSENSを試したことにより、
また悩みが生まれてしまいました。。。
初歩的な質問でお時間をとらせ、申し訳ないのですが、
何卒よろしくお願いいたします。。。
Motifさん
お返事が遅くなってすみません。
なるほど、ライン入力が前提であれば、最少に絞っておくのがいいと思います。
ここで調整するのはマイクプリアンプのゲイン調整なので、ラインであるのが
分かってれば最少がいいだろう、と。
ただし、ライン側の出力が極めて小さく、もう少し音量を稼ぎたいという場合は
レベルを上げるのは手だとは思います。ただ、レコーディングが前提であるならば、
このマイクプリで音量を上げるよりDAW側で調整したほうがS/Nはよくなるので
やはり最小にしておくのがよさそうですね。
藤本様
ご回答いただき、誠にありがとうございます。
シンセやミキサー等、ライン入力の場合はやはり最小にしぼるとのこと、
認識があっていたようで安心いたしました。
また、このたびは何度もご質問してしまい、大変申し訳ありません。
これからも記事を読ませていただき、勉強させていただきます!
入力レベル・ゲイン調整の関連で質問させてください。
先日 Forcusrite Scarlett 6i6 を購入し、手持ちのシンセのライン出力
から 6i6 に入力した際に、楽器側出力を最大近い状態にしても、思った
ような入力レベルが得られませんでした (手持ちの2台の楽器で確認)。
楽器側の「ライン出力」からの接続で、且つ出力も相当上げているのに、
ゲインツマミを半分かそれ以上回す (フロント端子/Line設定) とか、
Hi-Gain 設定にする (リア端子) といった対応が必要でした。
PC からの再生出力 (ヘッドフォン視聴) では何も問題なかったので、最
初は故障かとも思ったのですが、色々調べる中で、一口に「ライン入出力」
と言っても、業務系音響機器の +4dBu の基準と、コンシューマ系音響機
器の -10dBV 基準では、信号レベルが大きく異なることを知りました。
思ったほど入力レベルが得られない件は、6i6 のライン入力が +4dBu 基
準の業務仕様で、私の繋いだ楽器側の出力が -10dBV 基準のコンシューマ
仕様であるのが原因という理解であっているのでしょうか?
出力側のシンセも入力側の 6i6 も、基準入出力レベルについて仕様に明
記されておらず、音響機器の接続周りに関しては初心者なもので、理屈的
には妥当そうでも、自分の理解があっているのか不安でいます(^ ^ ;;;)
ちなにみ、基準値の違いを知ってから、改めて他の機材の仕様を見ると、
入力/出力や、入力端子間で、基準レベルの対応状況が異なっているもの
もあり、想定している利用シーンや接続機材等に関する各社・各製品の思
惑が見えてきて面白いですね。
出戻りDTM入門者さん
なるほど、そういう可能性はありそうですね。
基本的にコンシューマ用は-10dBV、業務用は+4dBuという信号レベルで単位が違いますよね。
+4dBu対応の機材はスイッチ(ドライバでの設定の場合もあります)で-10dBVにできますが、中には+4dBu固定のものがある可能性はあります。が、手元に6i6がなく、確かに仕様を見ても記載されていないので、確認してみる価値はありそうですね。今度、日本の代理店であるハイ・リゾリューションに聞いておこうと思います。
出戻りDTM入門者さん
先ほどハイ・リゾリューションから回答があり、やはり予想通り+4dBuとのことでした。
なかなか難しい問題ですね…
藤本様
早速確認頂きありがとうございます!
Scarlett シリーズの基準はやはり +4dBu だったんですね。
私の誤解 and/or 設定・機材の不具合でないことが分かりましたので、こ
れで安心してゲイン設定を高めにして使えます(笑)
ちなみに、ソフトシンセをいくつか使って気が付いたのですが、開発元が
海外 (Novation や UVI) のものだと、マスターボリュームやゲイン設定
を特に弄らなくても、比較的妥当な出力レベルを得られる一方で、KORG
Legacy Collection のものは、マスターボリュームを目一杯上げた上で、
更にゲイン調整機能を使って +6 ~ +12 dB ほどのかさ上げが必要でした
(多少のばらつきはありますが、概ねどの音色でも +6 は必要)
Legacy Collection の M1/Wavestation では、global setting の項目と
して明確に +6dB/+12dB のゲイン調整機能が付いていますので、やはり
これも -10dBV (≒ -8dBu) と +4dBu の基準差由来ということなんでしょ
うね。
はじめまして。歌い手志望です。コメント失礼します。
Audacityでミニプラグ接続のマイク(SONYのスタンド付きマイク。値段は3100円程)を使い録音したところ、高音や張った声が割れていたり、パソコンのノイズ(サーという音)が入っていたりと、散々な結果でした。
そこでキャノンプラグのマイク及びオーディオインターフェースを買おうと思ったのですが、これを買うことでAudacityでの録音は音割れ、ノイズの減ったものになるのでしょうか?
また、
http://www.amazon.co.jp/dp/B000GUBOYU/?tag=a8-affi-154012-22のマイクと、
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00B19JBW2/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=B00B19JBW2&linkCode=as2&tag=ikavocaloidp-22のオーディオインターフェースを使おうと思っているのですが、
このオーディオインターフェースに収録されているCubaseの限定版というのは、Audacityでの録音ののち、それをWAVファイルにしてCubaseで取り込みミックスするという使用法になるのでしょうか?
教えていただければ幸いです。
上で記した二つの商品を組み合わせ使った場合、なにか不都合は起きたりするでしょうか?
また、現在使用しているパソコンは極めて普通のデスクトップパソコンなのですが、普通のものであればオーディオインターフェイスは接続可能でしょうか?
教えていただけると幸いです。
たいちさん
やはりPCのマイク入力からのレコーディングでは、どうしてもそうなってしまいます。
しっかりしたマイクとオーディオインターフェイスを使うことで、そうした問題は大きく解決できるはずです。もちろん、使い方の問題はあるので、この記事にあるような話にも注意しつつですが。
SM58とUR22という組み合わせ、悪くないと思います。またCubaseがあれば、Audacityは不要ですし、AudacityはASIO非対応なので、音質やレコーディング性能を考えるとおすすめできません。Cubaseを使えば、ボーカルのモニターにリバーブをかける、といった使い方も可能になるので、断然歌いやすくなるはずですよ。
もちろん、まず慣れているAudacityを使いたというのであれば、使うことは可能ですし、Audacityで録ったWAVをCubaseにインポートして使うことはできます。
初めまして。いつも楽しく読ませて頂いております。コメント失礼いたします。
先日、Blue社のBluebirdマイクを購入しました。使用しているインターフェース「Audio Komplete6」に直接、接続しボイスをレコーディングしてみましたが、Gainのツマミを回していない状態でもピークにいってクリップしてしまい困りました。当然Gainを回すとクリップします。そこで考えたのが音は悪くなるという事ではありますが、ミキサーを間に接続してやる以外ないのかと思っているのですが他に方法はありますか?他に何かあればご教授お願いいたします。
kamimuraさん
ともに手元にないので、よくわからないのですが、何かの設定がおかしいのでは…という気がします。ただ、調べてみた限りでは、普通のコンデンサマイクなので、+48Vのファンタム入れて、マイク入力にさしていればいいだけのようですが。
もちろん、マイクプリ内蔵のミキサーを噛ませたり、単純にマイクプリを入れて、オーディオIFはライン入力にすれば、うまくいくはずです。ただゲインが一番搾った状態で、マイク入力がクリップするなら、何を入れてもダメのような気もしますね…。何か抜本的なところで間違っていることがあるんじゃないでしょうか…。
これと逆のこともありますね。
オンキョーの簡易型タイプのインターフェースだと、入力ボリュームを最大にしてもMTRのマスター出力でも不足になる。
オーディオインターフェースのクセに0dBピークを期待した仕様のものがあるというのは許せない事実ですねぇ~簡易型だからしょうがないのでしょうが。
しょうがなくヘッドホンモニタ出力からとったほうがレベルが高かったので、あとはキャプチャソフトで増幅処理。
使ったMTRはローランドVS-840、キャプチャソフトはAudacityです。
こんにちは!
ギター、ベースなどをLINE録音して制作している者です。
マルチエフェクターを使う際、hi-Zをオフにする事は知りませんでした!
そこまで大きな問題はないとの事でしたが、しばらくはマルチエフェクター使う際はオフにして様子をみようと思います!
また、確かに入力センシを最小にするとノイズものりにくく、聴いた限りいい音になるのですが、大変参考になりました!
今まではあくまで可能な範囲で大きな音で録ることに拘りすぎていて、多少のノイズは妥協して、EQで誤魔化していました(笑)
自分はクアッドのUA-55ですが、プリアンプとの兼ね合いも考えつつ、これから役に立てていきます!ありがとうございました!
ur22mk2を買ってpcとつないでみたのですが、出力される音声がディストーション以上にバリバリ鳴りながら音が割れます。もはや騒音です。以前に使っていた,soundblasterなどではなかった症状です。
何が悪いのでしょうか?
izaさん
ヘッドホンでも割れますか?また、同じ設定のまま別のオーディオインターフェイスやPC内蔵オーディオで聴いた場合、音が割れる現象はないですか?もしそうだとしたら、故障のように思うので、すぐに販売店に連絡して交換してもらうのがよさそうですね。
オーディオインターフェイスから出力される音なので出力デバイスのイヤホン、スピーカーどれでも割れます。pc内臓の音ではまったく割れません。
pcに静電気がたまることによって、音割れのようなノイズが出ることはありますか?
アース接続をしていません。
販売店に連絡しようと思います。
初めまして突然質問で申し訳ないのですが、
focusrite scarlett soloのインターフェイスを買いWindows10のPCに接続させ音は正常に
聞こえるのですがXLR-F、Mプラグのダイナミックマイクをインターフェイスに接続したら
砂嵐のようなノイズが入り、ろくに歌声を録音することができなくてこまってしまいまして
対応の方法があるのかどうかおしえていただけないでしょうか。
上記のくろというものです
自分が使っていたマイク【ECM-PCV80U】プラグインパワーでして
これにXLRマイク端子をつかっても供給されないから砂嵐のノイズしかならないんですかね?
くろさん
Scarlettなど、PC用のオーディオインターフェイスは基本的に、プラグインパワーに対応していません。マイクを一般的なダイナミックマイク、もしくは+48Vのファンタム電源対応のコンデンサマイクに変える必要がありそうですね。
初めまして。logicでifを使用しているものなのですが、ギターのレコーディングをつまみ最小にして録音した後に、ノーマライズを掛けて、アンプシミュレーターのエフェクトを掛けると、どんなエフェクトでも汚いというか、ノイズがとても酷くなってしまいます。最小で録音してした後にノーマライズは掛けずにコンプレッサーなどで上げたほうが良いのでしょうか?
ファさん
こんにちは。ifって何でしょうか?オーディオインターフェイスということですか?
そうであるとして、話を続けていきますね。
ファさんが、つまみを最小にしたのは、この記事を見てラインだから、という判断をしたのですか?だとしたら、そこがちょっと間違いです。ギターはラインレベルの信号ではないので、適正レベルになるまでノブを回してあげていきます。
本来であれば、演奏する時点で、リアルタイムにアンプシミュレーターをかけないと、
なかなか上手く演奏できないのでは…と思います。その際にアンプシミュレーターが気持ちよくなるようにレベル調整すればいいわけです。
またノーマライズというのは最後に行うものなので、エフェクトに入れる前にかけることは通常しませんね。0dBにノーマライズしてしまった音をアンプシミュレーターに入れれば当然過大入力となってしまうので、酷い音になってしまいます。
遅れてすみません!無事解決致しました!ありがとうございます。
こんばんは
今回の記事で自分も似たような症状なのですが、windows10でStudio One artistを使って録音しているのですが、IFの入力ゲインを最低,PCの録音レベルを0にしても音が割れてしまいます。
どのようにすればよいでしょうか。
IFはPersonusのAudio Box itwo,マイクは同じくPersonusのⅯ7を使っています。
けーさん
マイクの入力を行うのなら、入力ゲインは上げないとまずいですよ。
PCの録音レベルというのは、Windowsの設定でしょうか?これはASIOを使うので関係ないはずですね。Studio OneのオーディオIF設定を確認したほうがよさそうですね。
記事とあまり関係ないのですが..
どうしていいかわからないので質問させてください。
ガレージバンドを最新のバージョンにしたらオーディオインターフェイスを通したヘッドフォンの音に謎のエフェクトがかかるようになってしまいました、、
ビットクラッシャー➕ディレイのようなエフェクトです。
きれいにエフェクトがかかるのでノイズでは無いように聞こえます。
Macbookpro本体のスピーカーからはエフェクト無しの音が出ます。
音量ゲージを見てみても、やはりmac内ではエフェクトが鳴っていないようです。
Midiキーボードを鳴らしても、ギターを接続して鳴らしてもインターフェイスを通したヘッドホンからは同じエフェクトがかかります。
使用しているインターフェイスはTaskamのus322です。
インターフェイス内のエフェクター類は全てoffにしています。
古いバージョンのガレージバンドを使用していた時はこのような症状は出ませんでした。
Midi→Pc→インターフェイス→ヘッドホンのインターフェイス→ヘッドホン間だけでエフェクトが掛かることはあるのでしょうか?
それともただの故障でしょうか?
よろしくお願いします。
Pfさん
そうですね、オーディオインターフェイス内蔵のエフェクトの可能性はあると思います。オーディオインターフェイスに何を使っているのかが問題になるわけですが…。もし、オーディオインターフェイスに内蔵エフェクトを持っていないとしたら、故障だと思います。
こんばんは。
Cakewalkでオーディオインターフェースを使ってマイクを録音しています。
その際、PCで流している音楽がマイクにも入力されて、自分の声のみのトラックが欲しいのに、それに重なってBGMまで1つのトラックとして書き出されてしまいます。
どうしてもオーディオインターフェースを使った方法で録音したいのですが、オーディオインターフェースの特性なのでしょうか?マイクをUSB接続できるものに代えるしかないのでしょうか?
カテゴリーとは少し違いますが、相談に乗っていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
ジェルマンさん
オーディオインターフェイス側の設定の問題だと思います。おそらくループバック機能があるオーディオインターフェイスであり、そのループバック機能がONになっているのではないでしょうか?これをオフにすることで、Cakewalkからの再生音を入れずに、マイクからの音だけを録音できるようになるはずです。
藤本様、こんばんは。
MacにてZoomの音声(音楽)をUSBMixer(Allen&Heath ZED-10、BEHRINGER XENYX X1204USB)で流そうと試みているのですが、配信先への音質が悪く困っております(Zoom、Facebookライブで検証)。
こちらの記事を参考に「ロー出し、ハイ受けの原則」を試みたのですが、やはり解決に至りませんでした。
なにか特別に留意すること、設定などございますでしょうか?
お手数おかけし恐縮ですが、ご教授いただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
Tomoyukiさん
今、この手の問題を抱えている人が急増していますが、ほぼ全員、原因が異なるのが実情です。どこに問題があるのか、切り分けて追及していくしか方法はなさそうです。そもそも、その状態でDAWにキレイに録れるのなら、ハード側はOKで、Zoomの設定であったり通信環境側です。もし、キレイに録れないのであれば、レベルの門ぢあやマイクの問題でしょう。1つ1つ順番に問題をつぶしていくしかなさそうです。
藤本様こんにちは。
これはかなり初歩的なミスかもしれませんし、藤本様の立場を考えると
控えるべき質問かもしれません。
ですがぜひともお力を貸して頂ければと思い、投稿させて頂きます。
最近機材を集め始めた初心者です。
今現在自分は、配信を始めたく自分の声を録音し、
簡単な音声の編集を目的にしています。
以下の機材を使用しています。
・マイク→SURE SM7B
・マイクケーブル→CANARE XLRケーブル
・オーディオインターフェース→Scarlett solo
編集ソフト→Audacity
問題が以下の通りです。
・マイクの音が小さく、オーディオインターフェースのGAINをかなり回さないと十分な音量が出ません。
・編集用ソフトに音声を取り込もうとしても音が小さく反映される+保存したはずの音声が無音で聞こえない。
尚今現在変換アダプタを取り寄せ中で、オーディオインターフェースに直接ヘッドフォンをつないでの音声確認はしていません。
もし差し支えなければお返事いただければと思います。
お忙しいところ大変恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。
室田さん
こんにちは。状況だいたい分かりました。
機材投資の仕方がややアンバランスかな…という気はしており、おそらく問題はマイクの使い方ではないか、と。
SM7Bという、結構高価なマイクを導入したようですが、それが配信目的には合ってないためだと思います。
ダイナミックマイクは基本的に、非常に大きな音量を拾うためのものであり、結構大きな声でしゃべる必要があります。
また、単一指向であっても、かなり近距離でしゃべる必要があるので、そこがうまくできていないのではないでしょうか?
コンデンサマイクだと、非常に繊細に音を拾いますが、ダイナミックマイクだと感度は低いので、マイクゲインも
めいっぱい上げないと十分な音量にならないです。
ただ、保存した音声が無音で聴こえないというのは理由がはっきりしませんが、WAVなどで保存し、通常のスピーカー
などでは音が小さすぎて聴こえなかったという可能性が高そうですね。あまり正しい方法ではないですが、Audacityでノーマライズをかけるなど、編集機能で音量を上げることで、聴こえるようにはなると思います。
藤本様
アドバイス頂きありがとうございました。
お礼、また報告が遅くなりすみません。
本件、ここまで時間がかかりましたが、先日ようやく理想の状態となりました。
今回力になったのは「1つ1つ順番に問題をつぶしていく」というアドバイスでした。
多くの情報に埋もれ混乱していた状態が、こちらのアドバイスで目の前のひとつのことにフォーカスし、
丁寧につぶして行った結果、今回の成果に至りました。
ちょっと大げさな話になってしまうのですが、今回のアドバイスでわたしの人生観もちょっと変わりました。
この事以外でも「目の前のことにひとつひとつ」を心がけたところ、仕事のみならず、普段の生活の中でも
力が分散せず、うまく行くようになりました。
オンライン配信の問題から今回は人生のおいて大切な学びを得ることができました。
壮大になってしまいすみません(^_^;)
でも、ホントのことなので。
この度はありがとうございました、重ねてお礼申し上げます。
Tomoyukiさん
無事解決したようでよかったです!お役に立てて幸いです。
藤本様、初めまして。コメント失礼致します。
本記事などを参考にしながらレコードをPCに録音したのですが、CDに比べて音が小さくなってしまいます。
オーディオI/FのLINE入力レベルを0dBを超えないギリギリまで上げてから録音し、DAWソフトでノーマライズなどの処理をしてもCD音源ほどの音量にはなりません。
無理にオーディオI/FやDAWソフトでゲインを強くすると当然ながら音割れします。
針圧やアンチスケーティングの調整、ターンテーブルを安定した場所に設置するなどは行っています。
使用機材と接続方法は、
ターンテーブル:Pioneer DJ PLX-500
↓
針:SHURE M44G
↓
オーディオI/F:ZOOM UAC-2
↓
DAWソフト:Cubase 10
というふうに接続しています。
PLX-500内蔵のPHONO機能を使用しているのでフォノイコライザーは接続していません。
自分なりにあらゆる策を講じてみたのですが改善されません。もし宜しければお力添え頂ければ幸いです。
t.kさん
レコードだと当然CDと同じレベルにはならないです。CDのレベルにするには現代のマスタリング処理が必要なのです。そうしたマスタリング処理をして再発売されるのが、最近のリマスターというわけなのです。
このレベルの違いは単なる音量ではなく、音圧の違いです。
そのため、ここに最近のCDなどで行っているマスタリング処理である、コンプレッサ・リミッター、そしてマキシマイザーを用いた音圧調整をすることでCDのような音圧になるのです。
つまり、とりあえず、ここまでの過程は問題なく、その後にマスタリング処理をする必要があるというわけですね。
藤本様、お返事頂きありがとうございます。
素の音声を取り込むことに意識が行き過ぎてリマスタリングについて考えが及んでいませんでした。
藤本様のアドバイスのおかげで一つオーディオに対する理解が深まりました。ありがとうございました!
ps いつもDTMステーションの記事を楽しく拝読しております。これからも陰ながら応援しています。